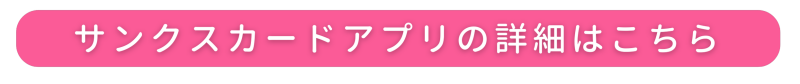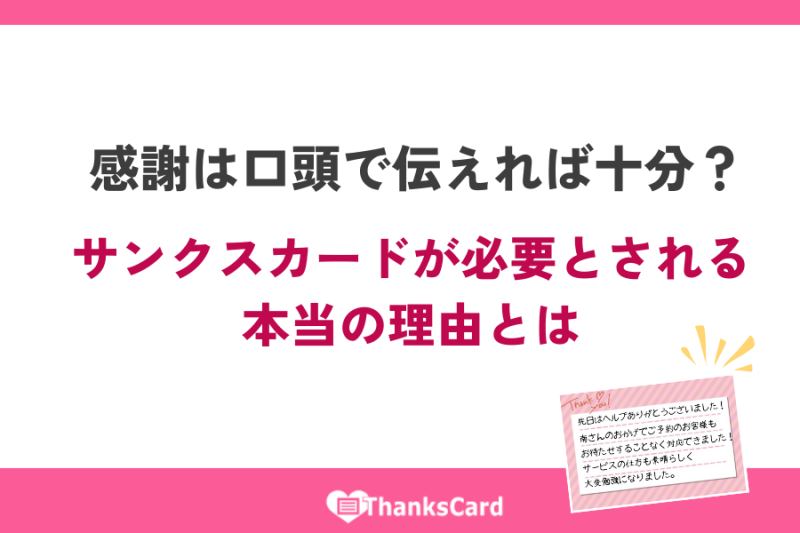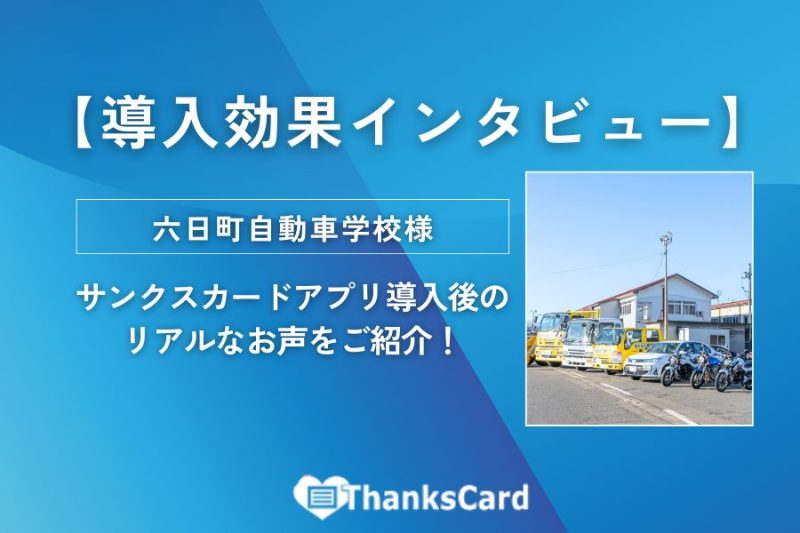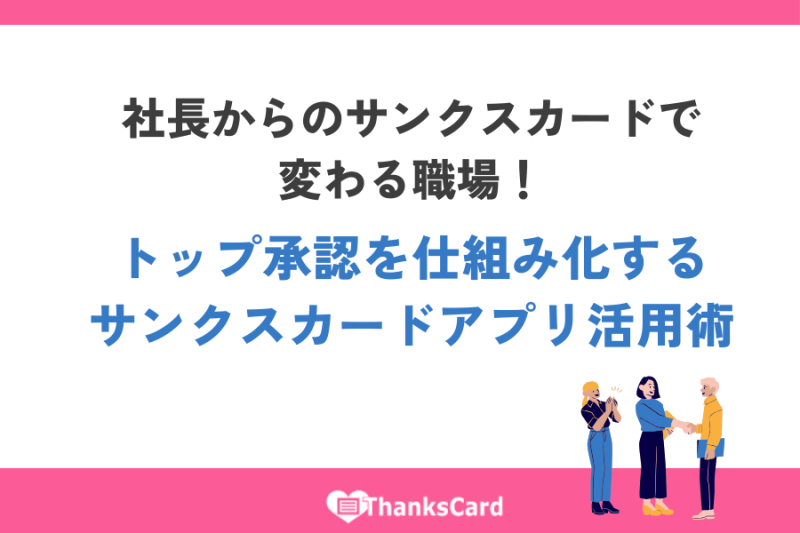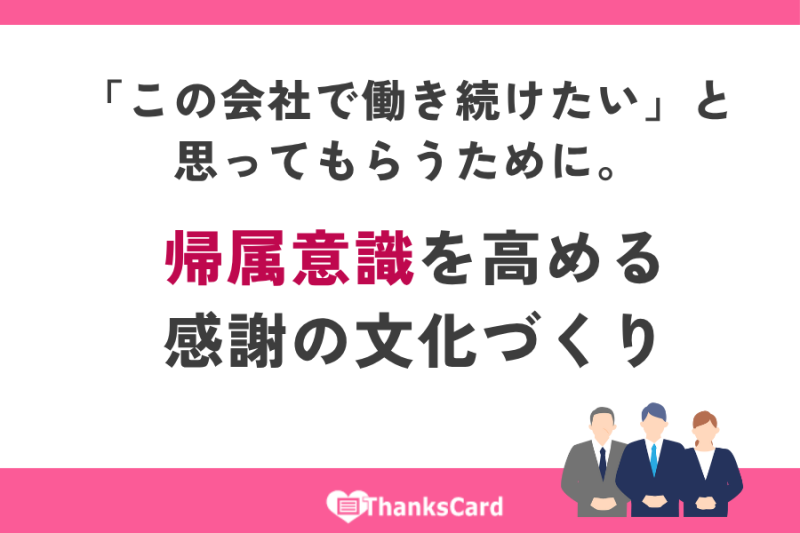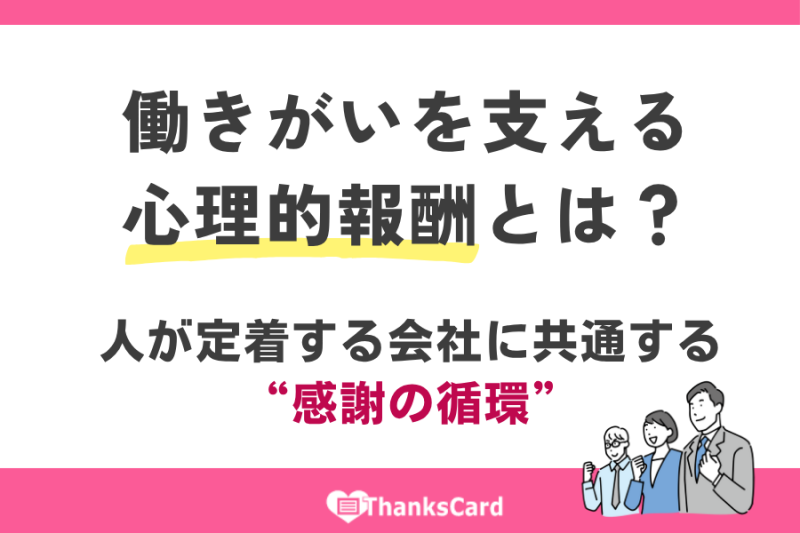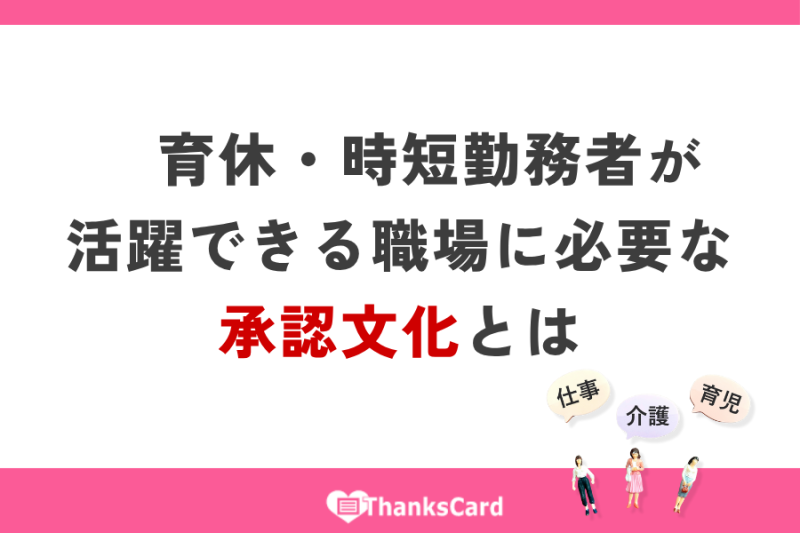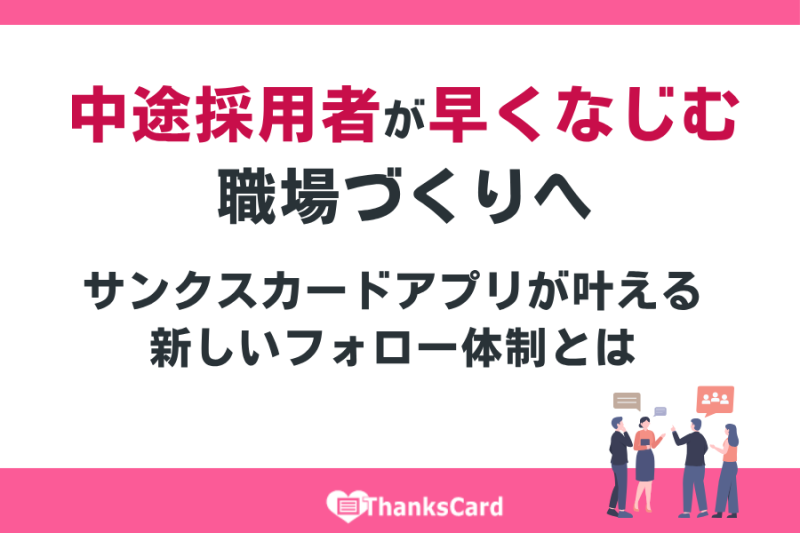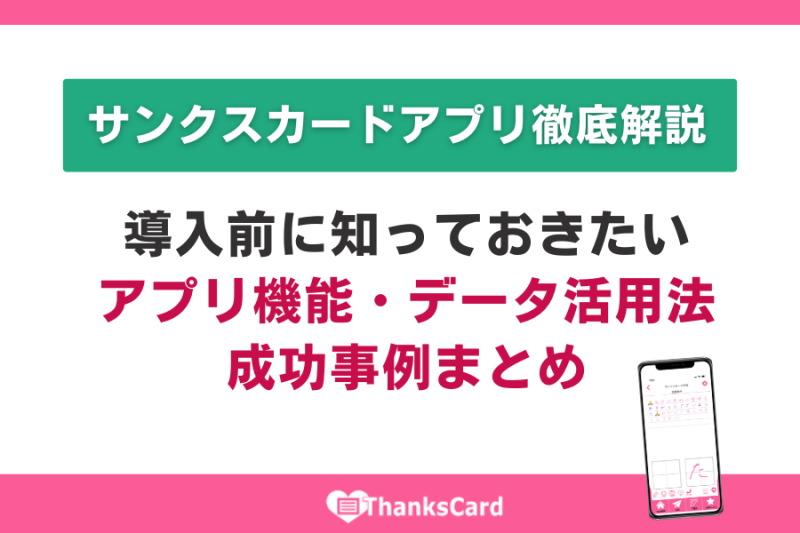「最近、支社の様子が見えにくい」
「地方拠点の声が、本社に届いていない気がする」
そんな違和感を抱いたことはありませんか。
全国に拠点を展開する企業にとって、距離や時間帯の違い、情報伝達の偏りは避けがたい課題です。
業務そのものは滞りなく進んでいても、現場では「自分たちは置き去りにされているのでは」と感じる瞬間が増えていきます。
本社と支社の間に、どこか目に見えない“壁”がある。
そんな空気が漂い始めたとき、それは組織の分断が静かに進んでいるサインかもしれません。
支社や地方拠点が感じる孤立感は、やがてエンゲージメントの低下や離職へとつながっていきます。
けれど、早い段階でその兆しに気づき、正しく対処すれば、組織全体のつながりを取り戻すことは十分可能です。
本記事では、支社の孤立が生まれる背景を紐解きながら、 物理的な距離を越えて“人と人”をつなぎ直すための具体的な方法、そしてその実践に役立つツールもご紹介します。
| 01|なぜ拠点間コミュニケーションは難しいのか? 02|拠点間に届く「ありがとう」が、孤立を変えていく 03|拠点を越えて人がつながる いま選ばれているサンクスカードアプリ 04|おわりに お問い合わせはこちら |
01|なぜ拠点間コミュニケーションは難しいのか?

支社や地方拠点で働く人からは、よくこんな声が上がります。
たとえば、メールは届いているものの、本社が何を考えているのかが見えてこない。
現場でどれだけ頑張っても、誰も気づいていないような気がする。
こうした感覚は、少しずつ働く人の心を離れさせていきます。
連携の難しさは避けられないとしても、それを放置すれば、やがて組織全体の一体感が損なわれ、情報も人もつながらない状態に陥ってしまいます。
とくに、次のような兆候は注意が必要です
1. 情報は届いているのに、共通認識が育たない
本社からの資料や指示は、形式としては正しく共有されているけれど、支社側では「また来たか」「今回は自分たちには関係なさそう」と、受け流されてしまうケースが少なくありません。
一方向の通達だけが繰り返されるうちに、現場は“聞くだけ”の姿勢に変わり、自然と発信しなくなっていきます。
気づけば、本社と支社の間に、見えない“理解のズレ”が生まれているのです。
2. 現場の努力が認識されず、熱量が落ちていく
クレーム処理やトラブル対応、繁忙期のやりくりなど、地方の現場では目立たない努力が日常的に行われています。
しかし、その頑張りが正当に認識されなければ、徐々にモチベーションは下がっていきます。
「誰も見ていない」
「やってもやらなくても同じ」
そんな思いが積み重なると、社員同士の協力も薄れ、やがて組織そのものの活力が失われていきます。
3. 会議では見えない“本音”が置き去りにされる
定例会議やオンラインミーティングは開催されていても、実際に交わされているのは報告と確認だけ。
本音や違和感、ちょっとしたつまずきは、話題に上ることなく見過ごされがちです。
「どうせ言っても伝わらない」
「言うほどのことでもないし…」
そうして支社側の声は閉ざされ、表面的な平穏の裏で、課題が静かに蓄積されていきます。
4. 支社ごとの文化や温度感が、分断を深める
拠点が増えるほど、それぞれの現場で独自のやり方や雰囲気が育っていきます。
それ自体は組織の多様性として歓迎すべきことですが、「うちはうち」「本社は関係ない」といった空気が定着してしまうと、企業全体の方向性や価値観がバラバラになってしまう恐れがあります。
“うちのやり方”が強くなりすぎると、全社的な変化にも反発が生まれやすくなり、結果としてまとまりにくい組織へと変質してしまいます。
このような“つながらない状態”が続けば、離職や人材定着の悪化だけでなく、
企業としての柔軟性や競争力をも奪いかねません。
では、どうすれば物理的な距離を越え、支社や拠点との信頼関係を築いていけるのでしょうか。次のセクションでは、その糸口となる“ある習慣”についてご紹介します。
02|拠点間に届く「ありがとう」が、孤立を変えていく
拠点間のコミュニケーションがうまくいかない一因は、「お互いの頑張りが見えないこと」にあります。
どれだけ目の前の業務に力を尽くしても、それが他拠点に伝わる機会は限られており、結果として“孤立感”が生まれてしまいます。
たとえば、
地方拠点で新しいマニュアルを作成したとしても、それが全社的に知られないまま埋もれてしまう。
あるいは、他拠点のトラブル支援に動いた社員がいたとしても、「そんなことがあったのか」と後から気づかれるだけで終わる。
このように、貢献は存在しているのに、認識されていない状態が続けば、社員同士のつながりも信頼も育ちにくくなります。
そんなときこそ力を発揮するのが、「ありがとう」という感謝と承認の一言です。
感謝のやり取りは、ただの礼儀や挨拶にとどまりません。
言葉にされることで、誰が何をしてくれたのかが社内で共有され、相手の存在や取り組みへの理解が深まっていきます。
たとえば、ある営業所が自作した業務マニュアルを、別の支店が参考にしたとします。
その支店の社員が「助かりました」と感謝を伝えるだけで、関係性は変わります。
さらにそのやり取りを社内で共有すれば、「こんな工夫をしている拠点があるんだ」「うちでも試してみよう」と、組織全体の視野と行動が広がっていきます。
これは、単なる感情の交流ではなく、組織の“血流”を生む行動だと言えるでしょう。
実際に感謝を社内で循環させている企業では、以下のような工夫を取り入れています。
・感謝のやり取りを社内ポータルや掲示板で紹介する
・毎月の社内報や朝礼で、拠点間の交流エピソードを取り上げる
・他拠点への感謝を社内表彰や評価制度に反映する
こうした見える化の仕組みがあることで、社員同士の関心が生まれ、物理的な距離を越えた関係づくりが可能になります。
反対に、感謝の言葉が表に出ない状態では、
「評価されているのは本社や一部の拠点だけ」といった不満が広がりやすく、協力よりも対立が生まれやすくなってしまいます。
だからこそ、感謝が自然とやり取りされ、社内に流通する“仕組み”を持つことが、拠点間コミュニケーションを改善する鍵なのです。
次のセクションでは、こうした感謝の習慣を無理なく定着させる仕組みとして、多くの企業で導入が進んでいるサンクスカードアプリについてご紹介します。
03|拠点を越えて人がつながる いま選ばれているサンクスカードアプリ
感謝の言葉が、拠点を越えて自然に行き交うようになれば、組織はゆるやかに変わっていきます。
ただし、それを日々の中で継続していくには、「伝えるきっかけ」や「仕組み」が必要です。
そこでご紹介したいのが、エヌエスケーケーが提供するサンクスカードアプリです。
このアプリは、従来の紙のカードと同じように感謝を伝えられるだけでなく、拠点間のつながりを育てるための工夫が随所に詰まっています。
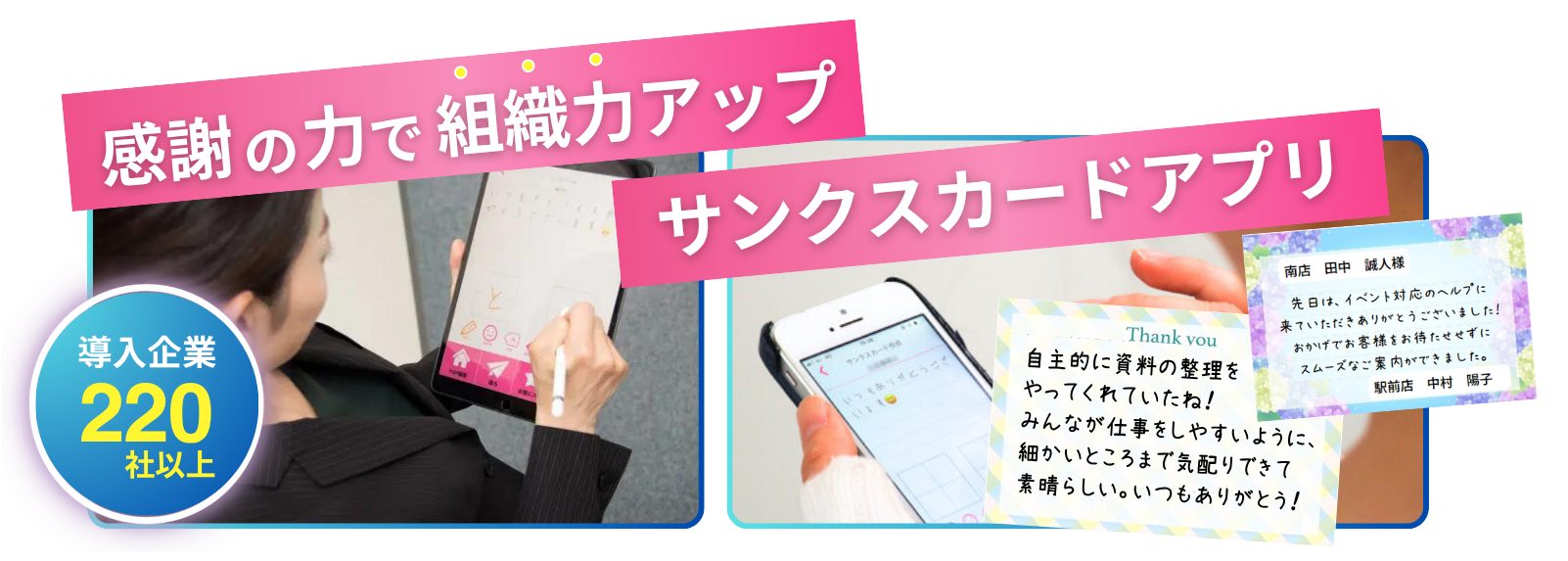
たとえば、こんな機能があります
・スマホやPCから手軽に送信できる
指やタッチペンで手書きできるほか、キーボード入力にも対応。相手に気持ちが届きやすい仕様です。
・送受信履歴を自動で集計・可視化
拠点ごとの送受信数を集計でき、部門間のつながりや活発度が“見える化”されます。
・ランキング機能
誰が多く感謝を送り、誰が多く受け取っているかがわかり、社内表彰や朝礼にも活用できます。
・社内掲示用のポスター出力(オプション)
ランキングなどをビジュアル化し、職場で共有可能。自然な“広がり”を生み出します。
・CSV出力で表彰・人事評価にも対応
定量的に感謝のやり取りを蓄積できるため、制度との連携もスムーズです。
・複数拠点に対応した組織設定
本社・支社・営業所など、企業の階層構造に合わせて柔軟に運用できます。

実際の事例|サンクスカードアプリで拠点間の課題が改善された企業様の声
【A社様】拠点異動による離職率が改善へ
ある製造業のA社様では、方針としておよそ3年ごとに拠点間の異動を行っておられました。
しかし異動先での関係構築がうまくいかず、異動後1年以内の離職が一定数発生してしまうという課題を抱えておられたそうです。
こうした背景から、拠点間での事前接点を生むことを目的として、サンクスカードアプリをご導入いただきました。
いただいたお話では、導入後、日々の中で「〇〇の業務助かりました」「こちらでも参考にしています」といったやり取りが拠点を越えて行われるようになり、異動前から“顔が見える関係”が生まれるようになったとのことです。
実際に人事ご担当者様からは、「導入以降、異動後の定着率が明らかに改善された」というお声を頂いております。
さらに、サンクスカードのやり取りを社内報で紹介したことで、社内全体に“拠点を越えた交流の文化”が根づいてきた実感があるとも伺いました。
【B社様】拠点ごとの分断を、可視化と評価につなげて解消
B社様では、各支店が独立的に動いていたことから、他拠点の状況や貢献が把握しづらいという課題を感じておられました。
とくに、「本社以外の取り組みが評価されにくい」という声が一部の社員から上がっていたこともあり、改善のためにサンクスカードアプリをご採用いただきました。
導入後は、拠点間での感謝のやり取りをポスター化して本社に掲示する仕組みを構築。
この取り組みをきっかけに、「離れた支店でも、きちんと見てくれている」という安心感が広がり、感謝を起点とした交流が活性化したと伺っています。
また最近では、カードの送受信データを活用し、部署横断の協力体制や成果に対して、社内表彰や人事評価で活かす試みも進めていらっしゃるとのことでした。
社員の皆様からは、「会社全体の動きが見えやすくなり、他拠点にも声をかけやすくなった」「孤立感がなくなった」といったご感想も多く寄せられているそうです。
企業ごとに背景や課題はさまざまですが、共通して言えるのは、感謝の気持ちを“仕組み”として流通させることが、距離を越えた信頼関係づくりの土台になるという点です。
拠点が増えるにつれて、業務は回っていても“気持ちの交流”は減りがちになります。
サンクスカードアプリは、そうした静かな孤立にやさしく働きかけ、企業全体をゆるやかにつなぎ直すツールです。
拠点を越えて感謝の気持ちを伝え合うことで、自然なつながりが生まれ、 社員一人ひとりの行動や気遣いが“見える化”されていきます。
その結果、離れた拠点同士にもあたたかいコミュニケーションが育ちはじめ、組織に安心感と一体感が戻っていきます。
拠点間コミュニケーションに課題を感じている方は、ぜひ一度、導入企業様の事例や機能の詳細をご覧ください。
04|おわりに お問い合わせはこちら
拠点間の分断や、気持ちのすれ違いは、日常業務の中で静かに積み重なっていきます。
業務は回っているのに、どこか孤立している感覚がぬぐえない…。
そんな違和感に気づいたときこそ、職場の空気を整えるチャンスです。
サンクスカードアプリは、感謝の気持ちを日常の中でやり取りできるシンプルな仕組みです。
特別な研修やルールを設けなくても、社員一人ひとりのつながりを自然に育てていくことができます。
実際に、すでに多くの企業様で、拠点間の分断をやわらげ、社員同士のつながりを可視化するツールとしてご活用いただいています。
人事異動後の定着率向上、支店間の協力体制の強化、離職率の改善といった成果も現れており、組織全体の風通しを良くしたいとお考えの企業様に、きっとお役立ていただけるはずです。
サンクスカードアプリについてのお問い合わせは、下記フォームよりお気軽にご相談ください。
サンクスカードアプリは現在、初月無料キャンペーン実施中!
「まずは試してみたい」という企業様も安心してご利用いただけます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

低価格で導入コストの心配いらず!
サンクスカードについては、
下記フォームより気軽にお問い合わせください。
▼▼▼
お問い合わせはこちら
運営会社
 株式会社エヌエスケーケー
株式会社エヌエスケーケー
コミュニケーションサポート
営業時間 9:00〜17:00(土日祝日はお休み)
〒657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町4丁目1-1
ウェルブ六甲道2番街5階
ご安心ください!
導入、運用にあたり
1社1担当者制で徹底してサポートいたします。
導入前でも、気軽にご相談くださいませ。
お申し込み
〜導入までの流れ
担当営業から連絡
弊社担当営業からすぐにご連絡。お申し込み内容を確認させていただきます。
弊社にて登録作業後、運用開始
登録作業完了後にご連絡差し上げます。お客様からの必要ファイルを受領後、最短5営業日で運用開始になります。
株式会社エヌエスケーケー
個人情報保護方針
株式会社エヌエスケーケーは、通信機器関連商品の開発、販売及びビジネスコミュニケーションコンサルタント事業を運営する上で、お客様の個人情報がプライバシーを構成する重要な情報であることを深く認識し、業務において個人情報を取り扱う場合には、個人情報に関する法令及び個人情報保護のために定めた社内規定を定め、また、組織体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めることにより、お客様を尊重し、当社に対する期待と信頼に応えていきます。
法令・規範の遵守
私たちは、個人情報に関する法令、規範及び社会秩序を遵守し、個人情報の適切な保護に努めます。
個人情報の取得、利用、提供
私たちは、事業活動の範囲内で個人情報の利用目的を特定し、その目的達成のために必要な限度で公正かつ適正に個人情報の取得、利用及び提供を行います。また、取得した個人情報の目的外利用をしないよう処置を講じます。
個人情報の適切な管理
私たちは、私たちが取り扱う個人情報について、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えいなどの危険を十分に認識し、合理的な安全対策を実施するとともに、問題が発生した場合は適切な是正措置を講じます。
継続的改善
私たちは、個人情報保護に関する管理規定及び管理体制を整備し、全社員で徹底して運用するとともに定期的な見直しを行い、継続的な改善に努めます。
問い合わせへの対応
私たちは、私たちが取り扱う個人情報について、本人から開示、訂正、利用停止及び苦情相談等のお問い合わせがあった場合は適正に対応します。
2013年7月5日 制定
2025年4月1日 改訂
株式会社エヌエスケーケー
代表取締役社長